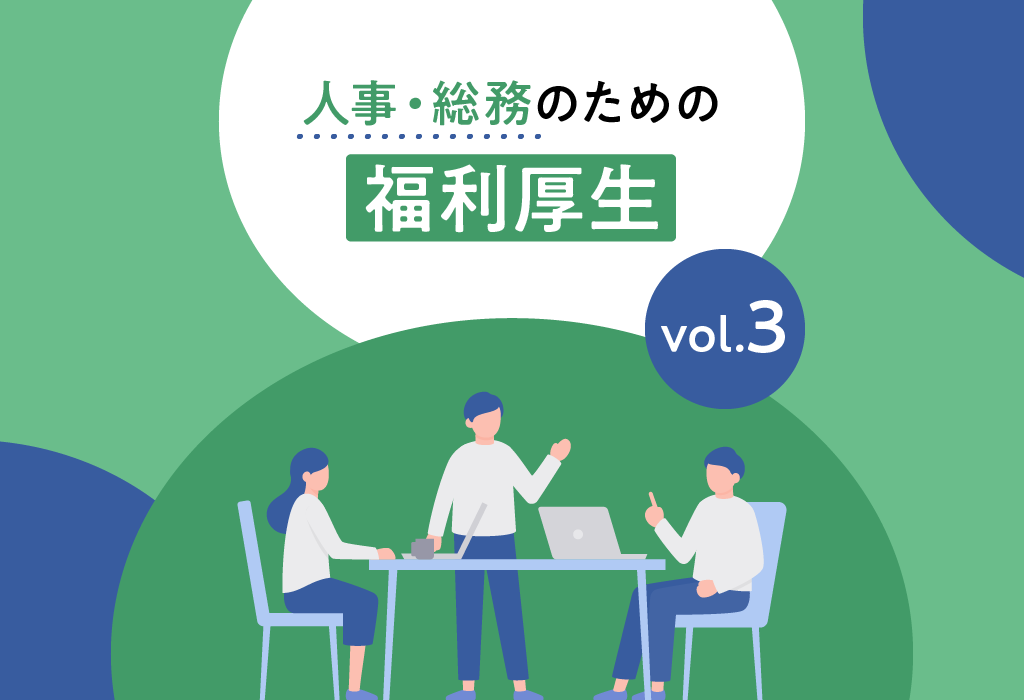社宅の知識
2025.07.09
【人事・総務のための福利厚生】連載⑦フィナンシャルウェルビーイングと福利厚生

好評連載中の「人事・総務のための福利厚生」です。福利厚生をわかりやすく解説しますので、人事・総務以外の方にも楽しんでいただけます。
私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する株式会社労務研究所の可児俊信(かにとしのぶ)です。福利厚生の事例の蓄積からたくさんお伝えします。
手伝っていただくのが、ハウスメイトパートナーズ従業員のSさんです。
【前回の記事はコチラ】

S
Sです。よろしくお願いします。この連載では、最近、よく耳にする人事用語を取り上げています。今日はフィナンシャルウェルビーイングです。

可児
ウェルビーイングは、連載第3回でお話ししました。健康に限らず、より広い意味で使われます。従業員が仕事に専念でき、高いパフォーマンスを発揮できるには、心身が健康であることだけでなく、社内外の人間関係・コミュニケーションが上手くいっていること、さらに生活や経済面での不安がないことも欠かせないからです。

S
従業員のフィナンシャルウェルビーイングを支えるのが、資産形成ですね。会社は既に福利厚生制度で資産形成を支援しています。その目的は何でしょうか?

可児
主な理由は、先ほど挙げたのと同じ理由です。従業員が仕事に専念でき、安心して働ける環境づくりですね。資産的に明るい将来があれば仕事にも身が入ります。そうした支援をしてくれる会社への感謝も生まれます。だから資産形成支援は長期勤続に繋がります。

S
フィナンシャルウェルビーイングには資産形成だけでなく保障も含まれるのですか?

可児
多くの専門家は資産形成の重要性を説いています。でも人生は何があるか分かりません。失業したり、家が災害で無くなったり、家族を失ったりという思わぬことがおきます。思わぬアクシデントが起きると、資産形成の目標額も変わってきます。失業すれば、収入が減るので資産形成の目標額は変わります。家族が亡くなれば、収入が減るかも知れません。思わぬアクシデントが起きても、目標額を変えなくてすむのが保障です。

S
資産形成・保障の重要性はよくわかりました。でも、ウチの従業員は、総じて資産形成には関心が薄いです。熱心なのは1割くらいです。

可児
その原因は、ライフプランとかライフイベントが将来のことであり、さらに漠然としていること、もうひとつは会社がそれを詳しく従業員に伝え切れていないことです。よって、積立額などの具体的な数値目標が必要です。

S
日本人は投資にリスクを取らないと言われています。

可児
それは資産形成に目標額がないからです。例えば、「退職までに5,000万円貯めよう。でもこのまま貯蓄するだけでは4,000万円しかならない。だから投資して3%の利回りをめざそう」。そう考えて積極的にリスクをとるのです。目標もないのに、わざわざ資産が減るかも知れないリスクを取る人はいません。

S
確かにそうですね。

可児
ところで、資産形成・保障の福利厚生には、財形貯蓄、持株会、社内預金、Bグループ保険、GLTDなどがあります。でも、こうした制度は従業員規模が大きくないと、割高になったり、そもそも制度が導入できなかったりすることがあります。

S
小さい会社は、資産形成の福利厚生はどうしたらよいですか?

可児
中小企業の資産形成を支援する国の制度があります。イデコプラスと中退共です。イデコプラスは300名以下の企業、中退共は法津(中小企業基本法)上の中小企業の定義に当てはまる規模の企業だけが対象です。大企業は自分のスケールメリットでいろんな福利厚生ができます。それに対して中小企業はスケールメリットが乏しいし、福利厚生の専門従業員もいません。

S
だから国が中小企業のためだけの福利厚生制度を作ったんですね。

可児
イデコプラスは、従業員が給与天引きでイデコ(個人型確定拠出年金)に加入していることが前提です。会社はその従業員の掛金を会社の掛金を上乗せし、投資額を増やす仕組みです。会社は労使合計の掛金額を国に振り込めば、後は国がやってくれます。
中退共(中小企業退職金共済制度)も、会社は掛金さえ払い込めば、後は国が年金資産を運用して増やして運用してくれます。なお、中退共の場合従業員は掛金を出せません。従業員が退職したら、国が退職一時金や年金を支給してくれます。

S
中退共もイデコプラスも老後の資金準備が目的で似ています。

可児
違いは、中退共は会社がお金を出す制度、イデコプラスは従業員がお金を出して会社が補助する制度であることです。中退共とイデコプラスをセット導入できればなお良いです。
<次回へ続く>
可児 俊信
千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授
株式会社労務研究所 代表取締役/福利厚生専門誌『旬刊福利厚生』発行
企業や官公庁における福利厚生制度のコンサルティングを行う。福利厚生や企業年金などをテーマとした著書、寄稿、講演多数。
関連キーワード
SNSシェア
あわせて読みたい関連記事
おすすめ記事
-

プレゼントキャンペーン
2025.10.02
【特別企画②の応募は締め切りました】ハウスメイト50周年特別企画
- ハウスメイト
- グルメ
- ハウスメイトからのお知らせ
- おいしいもの
-

ハウスメイトの多彩なサービス
2025.08.28
不動産の売却・購入のご相談に、親身に寄り添う「ハウスメイトの不動産売買アテンドサービス」
- 転勤
- 人事・総務
- 福利厚生
- ハウスメイトからのお知らせ
- 社宅
- 借上げ社宅
- 社宅担当者向け
- 社宅利用者向け
- 社有社宅
- 社宅制度
-

個人向けサービス
2025.03.12
防災グッズは買わずに「借りる」が安心!サブスク型「メンテンナス付きレンタル防災セット」
- 個人向けサービス
- 防災
-
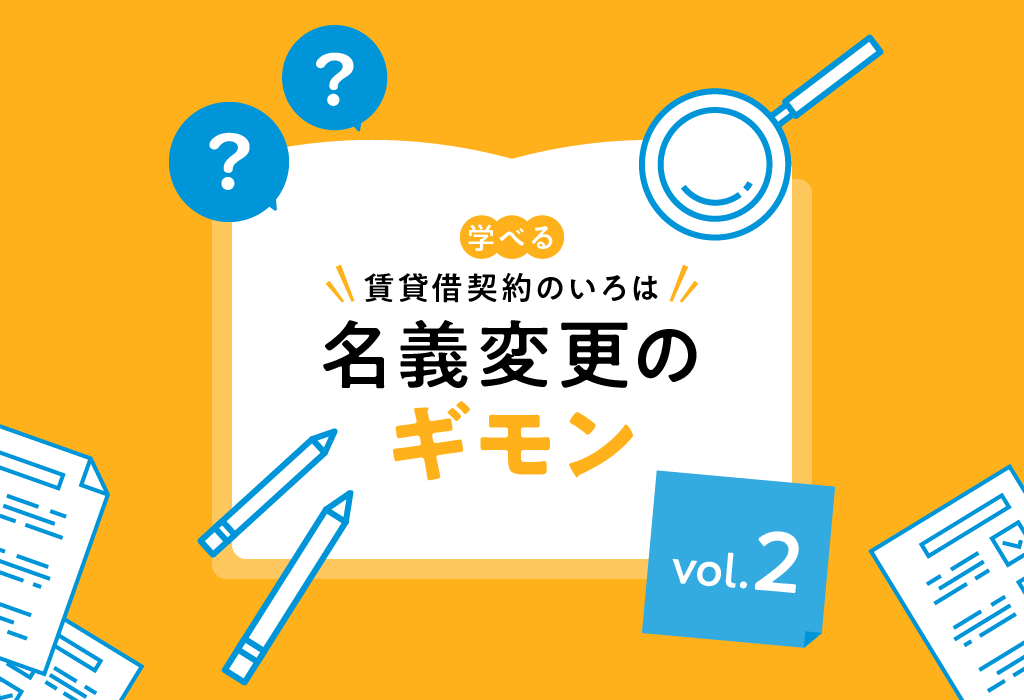
みんなの疑問
2024.10.07
【名義変更のギモン②】個人契約から法人契約へ契約名義を切替える際の注意点
- 賃貸借契約のいろは
- 社宅
- 社宅担当者向け
- 社宅利用者向け
- 名義変更
-
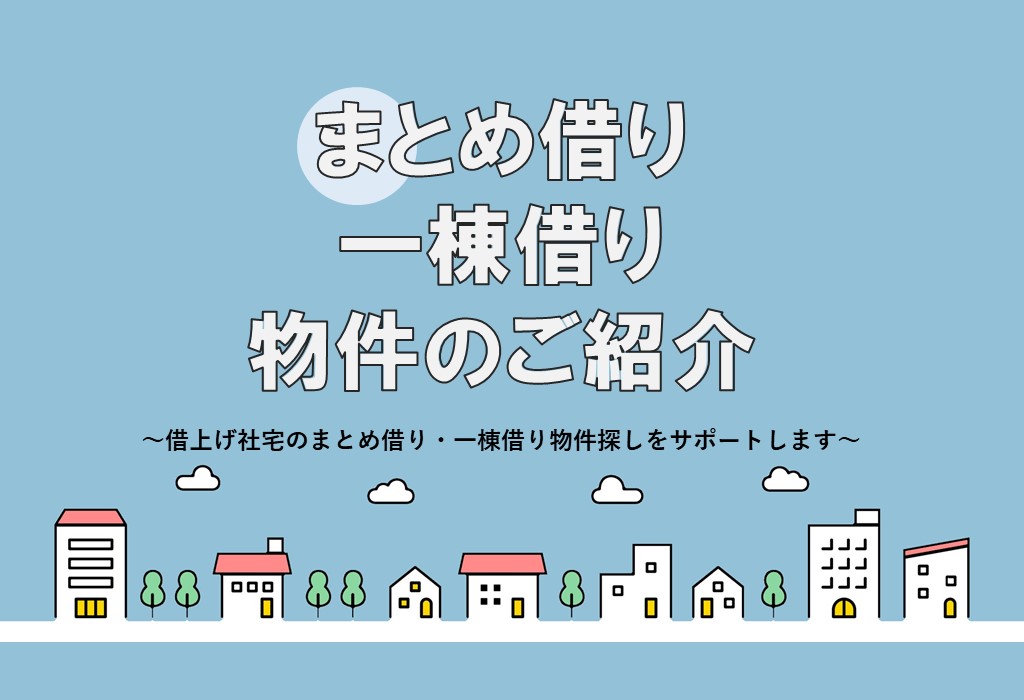
ハウスメイトの多彩なサービス
2025.06.06
借上げ社宅のまとめ借り・一棟借り物件探しをサポート
- 業務削減
- 転勤
- 人事・総務
- 福利厚生
- ハウスメイトからのお知らせ
- 新入社員
- 社宅
- 借上げ社宅
- 社宅担当者向け
- 社有社宅
- 社宅制度
- 制度見直し
-

Waプレミアム
2023.01.31
【賃貸仲介件数ランキング】ハウスメイトが2位になりました!(全国賃貸住宅新聞第1539号)
- ランキング
- 全国賃貸住宅新聞